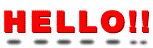
私の好きなオーボエ奏者達
順不同ですが、基本的にいかに音楽的かより、官能的か・インパクトがあるかが私の価値基準です。
- 第一弾:宮本文昭
- この人は言うまでもない有名人ですが一体どんな人・音なのでしょうか?
- 見るからに若そうですが今年で47才です。専門のスタイリストをかかえ、美人のスチュワーデスと結婚し一見派手そうですが非常に地味な声です。ぼそぼそとした声で雑踏の中で彼の声を聞き分けるのは至難の技です。よく管楽器の音色は声に似る(
息の出し方が同じなので)と言われますが例外中の例外かもしれません。
- 彼は音楽高校(桐朋)を卒業後ドイツに留学してしまったという変わり種で(今は大学を出てからが殆どだけど)、その時の話を以前「徹子の部屋」でやってましたが、よくよく顔を見ると目が大きいんですよ。それで一緒に行った料理のために留学しにいった人達からは「目玉ちゃん」と呼ばれていたそうです。
- ドイツではドイツバッハゾリステンで有名なヴィンシャーマン(奥さんは日本人)につき、第2・3弾で登場するロータコッホ、マンフレートクレメントに師事した後、エッセン市立交響楽団、フランクフルト放送交響楽団、を経て、現在ケルン放送交響楽団に首席奏者として在籍中。昨年11月より永年勤続休暇とやらで、1年間休みをもらって日本でいろいろ活動中とか。(4月は町田にも来るので聴きに行きます)われわれサラリーマンじゃあ考えられませんね。ただでさえ自由になる時間が多い放送オーケストラでこんな休みがもらえるなんて日本のプロが見たら泣きますよ。
- ここまで話してくるとまるで挫折を知らないスーパーエリートという感じですが、そうでないエピソードを一つ。僕が以前レッスンに行っていた先生が彼のことを多少知っていてこんな話をしてくれました。「以前バスで偶然会ったら、すごく自信なげな感じでこんなこと言ってたよ。「もう僕オーボエあきらめようと思うんです。才能ないし。それで日本に戻って喫茶店でもやろうかなって思ってるんです」」うーん。みんな悩んで大きくなるんだなあと思った話でした。
- 最初に彼を見たのは東京文化会館小ホールでのハープの篠崎史子とのリサイタルでした。高校の時「宮本文昭と仲間たち」という演奏会のチラシが貼ってあったけど、そのころはクラリネットをやっていたせいもありあまり関心もありませんでした。おしゃべりの入ったコンサートという触れ込みで(日経にも出ていた)期待していくと、しどろもどろで、皆の前で楽器を分解しはじめお決まりのオーボエ紹介をし始めました。
- リードだけで吹くとこんな音がします。
- 上管を付けチャルメラのメロディー。
そしてあの有名なR.コルサコフの熊んばちの飛行をやったのですが多少指が回らないところがあって最後に「レコードではうまく吹けているのでぜひ買ってください」などと言っていて妙に身近に感じたのを今でも覚えています。
- その後は楽器屋で2回ほど会いました。一回目は現れて用事が済んだと思った瞬間、店員からマジックを借りて楽器ケースにサインを頼んだところ、「こういう目立つところにはもっとホリガーとか偉い人のサインをするんだよ」と謙遜しながら言われたのですが「何をおっしゃいますか」と言ってサインをしてもらいました。その時一緒に行った友人は「恥ずかしいから止めろ」とか「くだらない」とか言っていたくせに、僕のサインが終わった後にいきなりリードケースを彼の前に差し出しサインを求めているではありませんか。(勝手なやつだ・・・)
- 二回目はリードを買いにある店にいたところ、バミューダで茶髪で変な鎖の付いた派手なサングラスを掛け、Tシャツにスポーツバッグを持った人がいきなり現れ、コールアングレのリードをくれと言って座りました。サングラスを取った瞬間「ああ!宮本文昭だ」とわかり妙に興奮したのを覚えています。その後2〜3分リードを選んですぐ出ていってしまいました。この時はサインをもらい忘れたので今でも後悔しています。
- 僕と彼の音との出会いは、僕が某病院に2週間ほど入院していた時に聞いたラジオでした。先程多少触れた「宮本文昭と仲間たち」というFM東京での番組でした。当時FM東京(現在のTOKYOFM)ではクラシックもそれなりに扱っていて、TDKオリジナルコンサートというので流れていました。
- 余談ですが、この番組終わり方が独特で、ライブなど拍手が終わらないうちから「今日のこの大変すばらしい演奏・・・」というナレーションが入るので、解説の続きかと思って録音スイッチを押すと「今日のこの大変すばらしい演奏に、もしノイズが入ったら・・・」という録音時にノイズが入らないようにする何かのオーディオ機器の宣伝で「せめて拍手が終わってからにしてくれー」と思っていたのは私だけではないはずだと思います。
- 話を元にもどすとして、この番組2回に分けて放送されましたが、今考えてもすごい?企画でこの何でもありの現在でさえ聞いたことがないことをやっていました。大きく分けて2タイプの形式で一つは普通の木管八重奏でもうひとつはオーボエアンサンブルでした。前者はいいとして、後者は想像するだけですごそうな感じですが、これがまたうるさいといえばうるさいんですが、一応集めたメンバーの多くがソリストなので派手で面白いんです。旋律と伴奏とくっきり分かれ、旋律は宮本文昭や北島章(現N響首席)などが担当し、伴奏にのまれるようなことはなくこれだけ目立てればリードで苦労してもいいかなと思える位でした。多分今オーボエをやっているのはこれを聞いたおかげかなと思ったりもしています。また8重奏の楽しみもこれを聞いてわかりはじめたと思います。最近多少考え方は変わってきたものの、いまだに8重奏は「オーボエと7人の伴奏者たち」というイメージがあります。だからあまり伴奏に入ることが多い8重奏はあまり好きではありません。(例えばベートーベン)で、この時のテープはバイブルとして未だに大事に取ってあり、たまに聞きます
。(中学のころから大学生の間に録音したテープ(500本程)は大事にとってあり、いつでも聞ける状態にあります。最近聞かないけど。)
- その後も彼の音は常に身近にあり、あるFMでモーツアルトのシンフォニーコンチェルタンテ(管楽器のソロのやつ)を聞いた時などは、感動なんてものじゃあないほど感動して毎日寝る前に聞くのが日課になる程でした。この時はまだフランクフルトのオケにいたころで、他のソリストも同じオケの人でした。ジョン・マクドナルドという変な名前の人がソリストでいてハンバーガーのイメージが強かった記憶があります。この演奏はいまだに体に染みついていて、以前大阪でこの曲のソロをやったことがありましたが(一応オケ伴奏で)あとでテープを聞くと宮本文昭を意識しているのがミエミエでした。
- また当然彼の出したCDは全部(といっても10枚程)買っているし、ピースのコマーシャルで演奏している姿は毎回目に焼き付けていました。
- 私だけでなくオーボエ奏者の多くは自分の好きな奏者のスタイルを真似ようと一回は試みるものである。何を真似るかが問題ではあるが、まっとうなところでは、アンブシュア(口の形)、リードの削り方、楽器のメーカー、姿勢などがあるが、笑えるものとして次のようなものがあった。(自分のものも含む)
-
- 大学の先輩でいつも楽器を持って右斜め上をぼーっと見てい人がいて「何をしているんですか?」と聞くと「宮本文昭の真似」と言う。よくリサイタルのチラシや雑誌などにある写真を真似ているのであった。
- 高校時代ある雑誌(音楽の友)をみたら宮本文昭が「本番前には必ずこれを飲むんです」といってリポビタンDを飲んでいるのを見て、毎回飲んだが効果なし。こんなもんで効くはずないか!と思ってがっかりしていました。ところがある時ふと楽器屋にあった雑誌を見ると宮本文昭がスポーツジムで運動している記事を見つけ読んでいくと「栄養ドリンク?あんなものはもうやめましたよ。あれをやめてから体がすっきりしてすごく気分がいいですよ!」。うーん複雑な心境。影響力が大きいんだから発言には注意してもらいたいもんです。
- また音楽の友に、宮本文昭が「ドイツのオケでは午前中にリハーサルがあって、本番は夜ということが多いので、午後は必ずひとねむりするようにしています。」というのを読んで本番前の2・3時間ほど寝て本番を迎えたら、体が眠ったままで意識はもうろうとし、指は回らず、休みの小節は数え間違えるし、タンギングはできなく最低だったことがありました。(一体どういう体をしているんだろう?寝方が違うのかなあ?)
- 昔は些細なことで音が変わると信じていて、レコードのジャケットで宮本文昭のリードを見ると、チューブと言われる金属部分にリードを巻き付ける糸が普通コルクの部分まで目一杯巻くのが、半分の位置で巻くのをやめていることに気づき「糸を巻く長さを半分にして、少しでもリードの振動を押さえないようにすればああいうきれいな音が出るのでは?」と思い、その仮説を楽器屋の店員に聞いたら、「そんなの関係ないよ。糸を節約しているだけじゃないの?」なんて言われ糸代にも困る人なのかなあとか、すごいめんどくさがりやなのかなとか思ったことがありました。
- その他思い付くままに彼に関することをいくつか紹介します。
- 以前彼の出したCDでビリビリした変な音がする楽器を使った曲がありました。ジャケットをみると」使用楽器オーボエミギンガ(Oboe
Mjganguih)と書いてあるじゃあありませんか。オーボエダモーレとかコールアングレとかミュゼット(小さいオーボエ)とかオーボエダカッチャとかは聞いたことがあったのだけれど、これは初耳でした。ところが友人から「あれはオーボエのベル(楽器の一番下の部分)を外してそこにギンガミを貼って吹いているだけだよ」と言われ、どうりで音程も悪いし、あのビリビリした音は銀紙だったのかあ!ミギンガって言うのは銀紙のことだったのかあ(つまりオーボエミギンガなんていう楽器は存在しない)ということに気が付いたのでした。
- 昨年ケルンが日本に来た時、新宿文化センターに聴きに行きました。幻想・チャイ5というとんでもないプログラムでしたが宮本文昭が吹くのを期待していきました。実際ステージに人が乗ると全然知らない人がオーボエの席に座っているのでちょっとがっかりして幻想を聞いているうちに3楽章に差し掛かりました。以前吹いたことがあるコールアングレのソロが始まり、変な解釈だなあと思っていると、バンダのオーボエが聞こえてきました。その直後静かながらも客席にざわめきが起こりました。そうです!音を聞くだけで分かってしまうほど強烈なインパクトのあるあのオーボエが舞台裏から聞こえてきたのです。まさかこんな形で現れるとは・・・。曲は牧歌的なものを表現しようとしているのになんて場違いな音色なんだろうと冷静に感じたのは曲が終わってからで、その時は「これで来たかいがあった」と思いました。
- 以上思い付くままに書いてみました。
ご意見、ご感想などは私(本橋)まで。
菊池明彦のオーボエの話−3−を読む
 [エッセイ紹介ページ]
[話−1−] [本橋家トップページ]
[エッセイ紹介ページ]
[話−1−] [本橋家トップページ]
[エッセイ紹介ページ]
[話−1−] [本橋家トップページ]